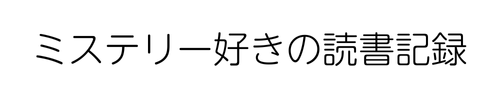あらすじ
大御所ミステリー作家・室見響子の遺稿が見つかった。それは彼女が小説家になる前に書いた『鏡の国』という私小説を、死の直前に手直ししたものだった。「室見響子、最後の本」として出版の準備が進んでいたところ、担当編集者が著作権継承者である響子の姪に、突然こう告げる。「『鏡の国』には、削除されたエピソードがあると思います」――。
削除されたパートは実在するのか、だとしたらなぜ響子はそのシーンを「削除」したのか、そもそも彼女は何のためにこの原稿を書いたのか……その答えが明かされた時、驚愕の真実が浮かび上がる。
登場人物
〈現代〉
・室見響子:大御所ミステリー作家。遺作として「鏡の国」を遺す。
・桜庭:響子の姪。小説を託される。
・勅使河原篤:響子の担当編集者。ベテランで慧眼の持ち主。
〈小説内の登場人物〉
・香純響:主人公。元アイドルであり、身体醜形障害者。
・新飼郷音:火傷を頬に負った少女。配信チャンネルで稼いでいる。
・吉瀬伊織:レストランで働く。相貌失認。響と郷音の幼馴染。
・久我原巧:響の同僚。頼れる先輩で、兄に幸秀がいる。
物語に出てくる病名
〈相貌失認〉先天性相貌失認とは視覚および知的能力に問題がないにもかかわらず、産まれた時から一生にわたる顔認知の障害を持つもの。本作では、伊織は相手の顔を正しく認識することが出来ず別日に会った場合、顔以外の場所でその人を認識している。しかし、人の顔を覚えるのが苦手だと感じるくらいで自分で相貌失認だということを自覚できていない人もおり、伊織も大切な人の顔を間違えてしまったことでトラブルに発展したこともあった。
〈身体醜形障害〉身体醜形障害(BDD)は不安障害の一種で、醜形恐怖症ともいわれる。自分の見た目について極度のこだわりがあり、外見についての考え事に多くの時間を費やすようになる。ほかの人から「全然普通だよ」「考えすぎじゃない?」と言われても、「自分は醜い。周りもそう思っているに違いない」と思い込み、コンプレックスがなくなることはないため、日常生活にも大きく影響する。
作中では身体醜形障害を発症している響に対して、心療内科の医師はSSRIという薬を処方している。脳のセロトニンを増やす薬で抗うつ作用もある。すぐに効果が出るわけでもないし、初めのうちは副作用も強く出ることが多い。徐々に副作用はなくなっていく。そんなつらい時期を経るのに薬の効果が出るかは人によって個人差がある。
作中では身体醜形障害の診断基準を4つ設けている。以下の4つである。
①外見の欠点にとらわれているが、その欠点は他者にとっては軽く見られる。
②外見の悩みによって過剰な鏡の確認や身づくろいなどをしている。
③外見にとらわれて激しい苦痛や生活する中での障害を引き起こしている。
④体型に関する悩みに呼応する摂食障害がある。
響は①前髪が変だと気にしているが他者からするとかわいいのに嫌味なのか?全然大丈夫なのに。と思われている。 ②鏡がある場所に行くと以上に前髪を見てしまうので鏡をデスクなどに置かないようにしている。 ③前髪についてずっと考えてしまったり、そのせいで大事な仕事中にも遅刻してしまうことがある。 ので3つに当てはまっていた。
メンタルクリニックに行くハードルの高さ
上司に勧められたからと響は心療内科を受診する。受診した際も「上司に強く勧められて、大したことないと思うのですが」と断りを入れている。また、受診している自分を心療内科にいる時でも恥ずかしいと感じている描写もあった。
前髪が気になっているだけでは度合いが他人よりも強くても問題意識は薄いかもしれないが、前髪が気になるからといって仕事の予定に遅れてしまうというのは病気を疑う理由としては十分なのでは?心の病気を認めるのには人によって個人差があると思うが、今の時代は受け入れやすくなっているのかもしれない。自分も心療内科に通っていた経験があるが、心の病気というのは明確にどこからが病気が発症しているのかわからないからこそ受診をする一歩目の判断が難しい。自分から、自分のことを心の病気かな?と思って病院を受診するのは、みんな大変な社会を生き抜いているのに自分だけ甘えている気がして行きづらいというのは分かる。実際に特に親しい友人にのみ相談をしたところ、心療内科を勧められたためそれをきっかけに「まぁ、よくなるかわからないけれどとりあえず行ってみるか」などという軽い気持ちで足を運んだ。
病院や症状の重さによると思うが、自分は医師と毎月話をしていく中で胃薬などを処方してもらっていた。段々病院に行く頻度を減らしていき、もう大丈夫かな?と思えたタイミングで通院をやめることを医師と話し合った。第3者から病院受診を勧めてもらうことはとても効果的だと感じる。なぜなら、響のように「友人に勧められたから」などと言い訳ができるから。言い訳だとしてもなんだとしても、自分が一歩を踏み出すことが出来るならそれは大いに意味のあるもの。また、薬を処方してもらうことで(毎回飲まなければいけないものとは別に気持ちが不安定になった時の強めの薬もあるのだが)、プラシーボ効果もあり何かあった時は薬があるから大丈夫だと飲まなくても安心材料になることもある。
しかしそれにしても、病院に通っている時や体に不調をきたしている時には他人にぺらぺらと話せるものでもなかったので、やはり病気を受け止めることのハードルは高いと感じる。
容姿が重視される世界
顔がかわいかったり格好良かったりする人はモテる。内定をもらいやすい。など、ルッキズムだなんだとささやかれる時代でもやはり容姿が自然と印象を左右しているのは否めない。悲しい世界だと思うがそれが現実。
いまは気軽に加工がアプリ等でできる時代。SNS上でコンタクトを取ってから現実世界でも会うなどがあり、実際に会うと違う人に見えて幻滅するかな?と、写真撮影では加工をどこまでしていいのかわからなくなってきている。ナチュラルに見えるけれど実際に見る顔よりもきれいになるアプリやフィルターもあって技術にびっくりする。
加工した顔が違いすぎてSNS上での自分と現実世界の自分を切り離して考えている人もいるほどだ。そうまでして実際の顔に自信が持てない世界にしてしまったのは紛れもない自分たちであり、またその被害に遭っているのも自分たちである。作中でも「この世界は鏡の国だ」と述べられている。絶えず鏡を突きつけられ、容姿で優劣をつけられ、自分の見た目について思い知らされている。
タイトルに込められた意味
室見響子が書いた『鏡の国』はクアドラプル(4つの)ミーニングを持っていた。
1⃣ ルイス・キャロル(鏡の国のアリスの作者)が相貌失認だったこと。
2⃣ 見た目重視の世の中を端的に表している。
3⃣ 『鏡の国のアリス』にも存在した、削除されたエピソードを示唆している。
4⃣ 室見響子の実体験として描かれたこの作品は鏡に映されたものように反転している=響子はものが経ちの登場人物の中の響ではなく、郷音の方だった ことを表している。
なぜ4⃣の要素を盛り込んだのか。理由としては、まず郷音はエキセントリックで読み手に共感してもらいにくいので語り手に向いていないこと。また、4つの意味を持たせるためもあり、鏡も4つに割られている。さらにはラストシーンに郷音が出てこないから。本当は削除されたエピソードの中に郷音も出てきているので、ラストシーンにもいるのだが。